ニュースリリース
メインイメージ
ニュースリリース


ニュースリリース
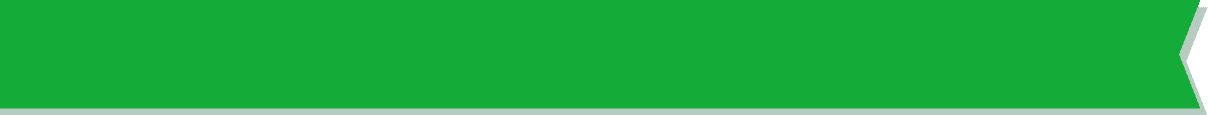 ニュースリリース
ニュースリリース
令和5年度第3回理事会が開催されました
令和5年度第3回理事会(全国理事会)が10月3日(火)に名古屋観光ホテルで開催されました。

理事会の開催にあたり西脇会長からご挨拶がありました。その概要としては、今回の全国理事会は、中部支部の関係者のご協力を得て、ここ名古屋で開催することが出来た事への感謝と御礼、ご出席頂いた皆様に平素から当協会の活動に対し、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げるとのお言葉がありました。その後、給食産業界の内容として、
①9月の初旬に「株式会社ホーユー」が経営破綻したこと。
このニュースは、この規模の企業の破綻としては、異例の取り扱いで、全国に知れ渡った。それだけ給食事業は、公共性、社会性が高いと今更ながら認識を深めたこと。
②「ホーユー」は、「150の受託件数で、23か所の営業所を21道府県に展開」と、これだけ聞いても、かなり広域で、かつ、まばらに事業所を展開していた事が分かり、「本部のコストは、相当高かったのではないか」と推察できたこと。
当該社長が、「ソフトランディングする為、関係各位と交渉してきたが、叶わなかったので、苦渋の決断をした」、「物価上昇に沿って、料金を上げられなかったから、経営が回らなくなった。やればやるだけマイナスになる。やむを得ず、営業を止めた。」、また、「食材費や人件費は高騰しているが、業界は非常に安いビジネスモデルは、崩壊している」と、声明を出したこと。
③私は、この「給食のビジネスモデルが崩壊している」という言葉に、最初は、同じ業界の経営者として、「責任を世の中のせいにするな」という、憤りを感じたと共に、「給食だから安くて当然だろ」という、乱暴な考えのお客さまの態度を思い出し、妙な共感も覚えてしまったこと。
そして、コロナ禍で請け負った食堂が、休止したり、テレワークや、オンライン授業の導入で、売上が減少していた最中に、食材と人件費の高騰が重なった状況は、全国の給食会社の大小を問わず、直面している問題であること。
④事実関係は不明だが、同社は、「競合他社との価格競争の中で、かなり無理をして受託していた」との報道もあり、飛び地のように事業所を受託し、営業拠点も多く広く展開していた為、いわゆる戦線を広げ過ぎた事は否めない。会社としての戦略を間違えた訳であること。
⑤だからこそ、このニュースを見た際に、私の考えは、確信に変わったこと。
給食の業界は、これまで、クライアントとの契約交渉に於いては、「想定される売上」と「期待される商品のクオリティ」、「望まれるアイテム数」を提供する為に、必要な食材費と人件費、そして、運営に関わる経費を算出し、競合他社の価格と競いながら、限界ギリギリの販売単価や委託費を、クライアントに提示するスタイルであったこと。
これは、デフレという時代を生き抜く為に、また、新たなクライアントを獲得する為、やむを得ず、給食の「相場感」を自ら破壊してしまった「安売り合戦」だったと言えること。
⑥しかし、時代は、急激に変化したこと。
今や、価格高騰が続いてきた「食材費」や「人件費」は、企業努力で解決する限度を超え、人材不足から発生する「派遣社員費用」や「人材紹介費用」も、「やむを得ない」という一言で、利益を削って吸収する事は、不可能な時代になったこと。
これからの契約は、かかった費用は、コストとして乗せる。堂々とクライアントに交渉する事が必須であると確信をしていること。
時代遅れの安売り合戦を繰り返している企業は、遅かれ早かれ「ホーユー」の二の舞になること。
また、毅然とした交渉態度は、これまでの値上げ交渉より、ハードなものとなるが、これら交渉の基礎となるのは、言うまでもなく「日々の美味しい食事」と「従業員の笑顔の接遇によるお客様満足度の維持」が必須なこと。
⑦給食会社の約3割は、赤字であること。
この事例を「他山の石」として、今こそ、私たちが作る“価値”を適正な“価格”で評価してもらえるよう行動して参ること。
⑧最後に、本日の理事会は、協議事項が2件と上半期の協会活動等の報告を受け、下半期に向けて、皆様からのご意見・ご提案をお願い申し上げますとのご挨拶がありました。
理事会の議案は、協議事項として第1号議案「会員の新規加入に関する件」及び第2号議案「相談役の設置に関する件」について、全会一致で承認されました。
報告事項は、①令和5年度中間事業報告として、ア.各支部の取組状況報告、イ.各委員会の取組状況報告、ウ.役付理事の職務執行状況報告、エ.事務局の事業報告、オ.第10回作文コンクール経過報告、②当面のスケジュールについて、③会員の退会について、④支部構成員の退会について、⑥協賛会社の入会についての報告がありました。

なお、理事会に先立ちまして、去る9月2日に当協会の理事でありました、富士産業株式会社 代表取締役 中村勝彦様がご逝去されましたので、故人のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。

第3回理事会 西脇会長挨拶
理事会の開催にあたり西脇会長からご挨拶がありました。その概要としては、今回の全国理事会は、中部支部の関係者のご協力を得て、ここ名古屋で開催することが出来た事への感謝と御礼、ご出席頂いた皆様に平素から当協会の活動に対し、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げるとのお言葉がありました。その後、給食産業界の内容として、
①9月の初旬に「株式会社ホーユー」が経営破綻したこと。
このニュースは、この規模の企業の破綻としては、異例の取り扱いで、全国に知れ渡った。それだけ給食事業は、公共性、社会性が高いと今更ながら認識を深めたこと。
②「ホーユー」は、「150の受託件数で、23か所の営業所を21道府県に展開」と、これだけ聞いても、かなり広域で、かつ、まばらに事業所を展開していた事が分かり、「本部のコストは、相当高かったのではないか」と推察できたこと。
当該社長が、「ソフトランディングする為、関係各位と交渉してきたが、叶わなかったので、苦渋の決断をした」、「物価上昇に沿って、料金を上げられなかったから、経営が回らなくなった。やればやるだけマイナスになる。やむを得ず、営業を止めた。」、また、「食材費や人件費は高騰しているが、業界は非常に安いビジネスモデルは、崩壊している」と、声明を出したこと。
③私は、この「給食のビジネスモデルが崩壊している」という言葉に、最初は、同じ業界の経営者として、「責任を世の中のせいにするな」という、憤りを感じたと共に、「給食だから安くて当然だろ」という、乱暴な考えのお客さまの態度を思い出し、妙な共感も覚えてしまったこと。
そして、コロナ禍で請け負った食堂が、休止したり、テレワークや、オンライン授業の導入で、売上が減少していた最中に、食材と人件費の高騰が重なった状況は、全国の給食会社の大小を問わず、直面している問題であること。
④事実関係は不明だが、同社は、「競合他社との価格競争の中で、かなり無理をして受託していた」との報道もあり、飛び地のように事業所を受託し、営業拠点も多く広く展開していた為、いわゆる戦線を広げ過ぎた事は否めない。会社としての戦略を間違えた訳であること。
⑤だからこそ、このニュースを見た際に、私の考えは、確信に変わったこと。
給食の業界は、これまで、クライアントとの契約交渉に於いては、「想定される売上」と「期待される商品のクオリティ」、「望まれるアイテム数」を提供する為に、必要な食材費と人件費、そして、運営に関わる経費を算出し、競合他社の価格と競いながら、限界ギリギリの販売単価や委託費を、クライアントに提示するスタイルであったこと。
これは、デフレという時代を生き抜く為に、また、新たなクライアントを獲得する為、やむを得ず、給食の「相場感」を自ら破壊してしまった「安売り合戦」だったと言えること。
⑥しかし、時代は、急激に変化したこと。
今や、価格高騰が続いてきた「食材費」や「人件費」は、企業努力で解決する限度を超え、人材不足から発生する「派遣社員費用」や「人材紹介費用」も、「やむを得ない」という一言で、利益を削って吸収する事は、不可能な時代になったこと。
これからの契約は、かかった費用は、コストとして乗せる。堂々とクライアントに交渉する事が必須であると確信をしていること。
時代遅れの安売り合戦を繰り返している企業は、遅かれ早かれ「ホーユー」の二の舞になること。
また、毅然とした交渉態度は、これまでの値上げ交渉より、ハードなものとなるが、これら交渉の基礎となるのは、言うまでもなく「日々の美味しい食事」と「従業員の笑顔の接遇によるお客様満足度の維持」が必須なこと。
⑦給食会社の約3割は、赤字であること。
この事例を「他山の石」として、今こそ、私たちが作る“価値”を適正な“価格”で評価してもらえるよう行動して参ること。
⑧最後に、本日の理事会は、協議事項が2件と上半期の協会活動等の報告を受け、下半期に向けて、皆様からのご意見・ご提案をお願い申し上げますとのご挨拶がありました。
理事会の議案は、協議事項として第1号議案「会員の新規加入に関する件」及び第2号議案「相談役の設置に関する件」について、全会一致で承認されました。
報告事項は、①令和5年度中間事業報告として、ア.各支部の取組状況報告、イ.各委員会の取組状況報告、ウ.役付理事の職務執行状況報告、エ.事務局の事業報告、オ.第10回作文コンクール経過報告、②当面のスケジュールについて、③会員の退会について、④支部構成員の退会について、⑥協賛会社の入会についての報告がありました。

理事会の様子
なお、理事会に先立ちまして、去る9月2日に当協会の理事でありました、富士産業株式会社 代表取締役 中村勝彦様がご逝去されましたので、故人のご冥福をお祈りし、黙祷を捧げました。